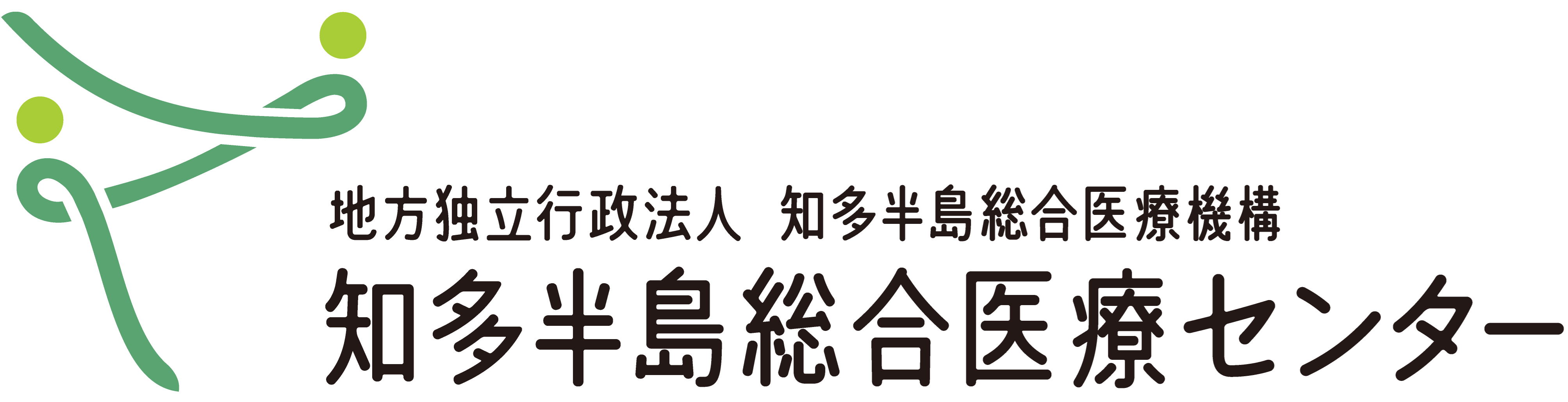渡邉 和彦 様
理事長
品田 正樹 様
理事
知多半島総合医療センターは、開院に至るまでの10年に及ぶ構想期間を経て、2025年4月新たに、半田市と常滑市の公立病院同士で経営統合を行い地方独立行政法人知多半島総合医療機構として出発しました。
医療実務に合わせた常動線デザイン、そしてLCIによって共創型で進めたロボットインフラを含む医療DXは、今後の医療課題を支える新たなモデルを示しています。
“ロボットが当たり前に走る病院”が地域にもたらすインパクトとは、そして、医療DX を推進する上で欠かせない考え方とは──。
本インタビューでは、LCIサービス導入・検証の目的や今後の展望などについて、理事長の渡邉 和彦様、理事の品田 正樹様にお話を伺いました。
現場の声に耳を傾けて辿り着いたDX
新病院について、公式サイトに「構想10年」と記載がありますが、改めて開院までの経緯と想いをお聞かせください。
渡邉様
知多半島総合医療センターは、半田市と常滑市の市民病院が経営統合し、新たな急性期医療の拠点として誕生しました。最初に「病院を建て替えよう」と決めたのは2015年ですね。
旧半田市立半田病院は築42年で、雨漏り・耐震・バリアフリーなど、何をとっても改善の余地がありました。その中で、東日本大震災によって津波リスクへの懸念が高まり、市民の声や市長選の結果を受ける形で高台への移転が決定されました。
当初の予定地は伊勢湾台風で浸水歴があり、建設場所については実に様々な議論が起こったんですよね。市民運動があったり、知事から“待った”がかかったり、まさに急転直下です。最終的に高台の農地を地権者の方々と交渉し、建設場所をゼロから見直しました。
「土地が決まるまでに5年」、そこから統合計画・地方独立行政法人化・資金調達が一斉に走り出し、気づけば10年。長いようで、振り返ればあっという間でした。

今回の開院にあたり、病院機能としても大きな改革を実施されたとのことですが、特に「医療DX」の役割はどのように位置づけられていましたか?
品田様
実は、最初はロボットの導入なんて全然考えてなかったんです(笑)
とにかく最新の医療機器を入れよう、そこからスタートしました。ロボットの話が出てきたのは3年くらい前ですね。当時は他の病院でもテスト段階で、当院でももちろん予算もついていない。「本当に必要なの?」という空気でした。
でも一方で、看護師さんたちから「人手が足りない」「夜勤が大変」っていう声がどんどん届いたのも事実です。この課題は病院としても本気で考えなくてはいけないなと感じていました。
渡邉様
最も重視したのは「人にしかできないことに集中するための環境づくり」です。ICTやロボットは、単なる効率化ツールではなく、スタッフが看護や診療に専念できる環境を整えるための支援基盤。あえて言うなら、私たちがDXで狙ったのは“便利”ではなく“解放”かもしれません。
私たちとしては、地域の人たちに「ここってすごく先進的な病院なんだな」と感じてもらいたかったのもありますが、何より一番大事だったのは、看護師さんたちの助けになることです。人手不足に関しては悲鳴にも似た声が届いていましたが、やはりそういう声に耳を傾けて、動いた病院であることをきちんと見せたかったですね。
“先端技術を入れたいから”じゃなくて、“現場のSOSを拾った結果としてのDX”だったということですね。
ワンフロア設計が生む、“人にもロボットにもやさしい”病院
新病院を実際に訪れて、病院の作り自体がとても特徴的だなと感じましたが、建設時にこだわったポイントはありますか?
渡邉様
知多半島総合医療センターは、外来の患者さんが1階で全部完結するようにワンフロアで設計されています。多くの病院は「階」で診療科診察室や検査エリア等を分けていて、エレベーターを使わないと移動できないと思うのですが、私たちはなるべく“横型”の構造を目指しました。

例えば診察室から放射線、検査、化学療法ができる場所まで、すべてが同じ階で済むので、2階に上がらなくてもいいようになっています。スタッフも患者さんも、わずか数十秒で、隣のエリアに移動できます。
2階はICUや手術室など、いわゆる「病院の心臓部」が集中しています。スタッフの更衣室や医局もそこにあるので、動線的にも無駄がなくて、すぐに動けるようにしました。
3階より上が病棟ですが、そのフロアもできるだけスタッフの動線も短くなるように設計したり、患者さんがなるべくエレベーターを使わずに受診や治療ができるように工夫されてます。
この構造は結果的に、ロボットの導線としてもとても効果的な印象があります。
渡邉様
そうかもしれません。動線が水平にできてるから、ロボットもスムーズに走れる。病棟のワンフロアを40メートルくらい確保して、エレベーターに頼らずに回せるようにしています。こういった“患者中心”と“スタッフ中心”の両方を考えた作りは、設計段階から「絶対に譲れない」ポイントでしたね。
だから今、病院の中でロボットがスムーズに動いてる様子を見ると、「ああ、設計から全部つながってるな」と実感します。「最初から意図してたわけではないけど、設計思想としてはぴったり合った」という感じですね。
品田様
ロボット導入に関しては、いろんな会社に話を聞いて、十数社のロボット企業に来てもらいました。将来的に各用途のロボットが共存できるシステムが必要だと考えていたのですが、そこで「これだ」と思ったのが、Octa RoboticsさんのLCIだったんです。
ロボットそのものではなく、インフラを見直すという観点はもちろん、他社と比べて、やはりその動線への馴染み方がとても自然だったんですよね。うちの病院は“横動線”が基本になっているので、その実務導線に合うかどうかが重要なのですが、LCIはその条件をきちんとクリアしていました。
「これはもう、なんとかして予算化しよう」ということになり、その頃には当時の院長だった渡邉理事長にも相談しながら、徐々に全体を巻き込んでいきました。
導入の決め手は「他社との共存を前提とした設計思想」
実務導線との相性についてより深く教えてください。数ある選択肢の中で、なぜLCIを選ばれたのでしょうか?
品田様
やはり「発展性」と「柔軟性」ですね。
もちろん様々なサービスを見比べて、各社それぞれに強みがありました。でも、LCIを最も魅力的に感じた理由は、「他社との共存を前提とした設計思想」だと思います。
「ひとつのロボットだけで完結しますよ」という姿勢ではなく、「将来的にいろんなロボットとつながっていく前提で基盤をつくりますよ」という考え方に、非常に可能性を感じました。
渡邉様
そこはものすごく重要でしたね。病院って、一度建てて終わりじゃなくて、5年後・10年後にどう進化していくかを考えないといけない。そのときに、拡張性がないシステムを選んでしまうと、後からどうにもならないんですよ。
品田様
もう一つ大きかったのは、導入支援のスピードと柔軟な対応力です。実際に話していく中で、「あ、これは現場にちゃんと寄り添ってくれる会社だな」と感じました。要望に対してのリアクションも早かったし、何より「こうすればもっと良くなりますよ」っていう提案が常に具体的でした。
結果的に、「1社で囲い込む」のではなく、あくまで“未来に開かれた設計”をしていたのが、Octa Roboticsさんだった。それが、最終的に「この会社と一緒に未来をつくっていけそうだ」と思えた決め手でしたね。

渡邉様
最初私もロボット導入の話を聞いたときは「本当に必要?」と半信半疑でしたが、実際に企画室からの話を聞いてみると、単なるスポット導入で終わる話ではなく、今後の病院内のあらゆる箇所で活用できそうな拡張性を感じました。
まだ他の病院での事例もない中でしたが、逆に「だったらうちがパイオニアになろう」という想いで決断しました。
歴史ある病院の中で、それを判断できるってすごいことだと思います。まるでベンチャー企業のようなマインドですね。
渡邉様
我々もベンチャーみたいなものですよ。だって、いつだって「先に走った者だけが新しい景色を見られる」でしょう?だから私は、常に現場の看護師にも企画室のメンバーにも、彼らが「チャレンジしてみたい」と思ったことに対しては積極的に手を挙げられるような環境にしたいし、長期的に見て判断して、判断したからにはぜひその背中を押してあげられるようにしたいと考えています。
品田様
実際この病院はとても働きやすいと思いますよ。
企画室の方もとても頷いてくださっていますね(笑)
ちなみに、ロボット導入自体は、実際にすぐ病院内の皆さんには受け入れられたのでしょうか?
品田様
そこは難しいところで、技術的にどんなに良くても「人の意識」が変わらないと、実装には至らないんですよね。だから「まずは見てもらう」「体験してもらう」というプロセスを重要視して、病院内で展示会や体験会の機会を設けるようにしました。
それを通して少しずつ「おもしろいね」「使えそうだね」という空気が生まれていって、それがやがて「じゃあ、やってみようか」につながっていったのだと思います。
今回の導入で、どのような変化や効果を期待していますか?
品田様
やはり私たちが一番期待しているのは、看護師さんたちの身体的・心理的な負担を軽減することですね。
特に夜間の対応は、本当に過酷です。スタッフの数が限られている中で、ナースコール対応をしながら、検体を運んだり、物品を取りに行ったりと、やらなくてはいけない業務が山ほどある。現場からは、もう「助けて!」「人手が足りない!」っていう悲鳴のような声がずっと届いています。
渡邉様
ロボットに任せられることはロボットに任せて、その分の“余力”を患者さんへのケアにまわせるようにしたいですね。たとえば、夜間に少しでもスタッフが落ち着いて対応できるようになれば、それだけでも安全性はグッと高まりますし、働く人の気持ちにも余裕が生まれます。
人手不足を“人数”で埋めるのではなく、“仕組み”で支える。そういうアプローチを、これからの病院は本気で考えていかなくてはいけないと思っています。
これは単なる“機械化”ではなくて、「人のためにどう技術を活かすか」っていう、病院の姿勢そのものを象徴するものなんですよね。
他の病院関係者から相談を受けたら、LCIをどのように説明・推薦しますか?
品田様
「インフラとしての強さ」を伝えたいですね。Octa RoboticsさんのLCIはマルチベンダー対応仕様のため 、建物・設備との連携や既存システムとの親和性に優れていると感じています。導入後の拡張や他メーカーとの共存にも耐えうる設計思想を持っているところは、ぜひともお伝えしていきたいところです。
今後、次の活用方法や改善点についても積極的に意見交換をして運用していきたいですね。拡張性の高いロボット連携プラットフォームだなと思います。
人・ロボットインフラ・病院で共創する「医療DX」
「病院でDXを推進する」上で、今後必ず押さえておくべき要素は何だとお考えですか?
品田様
「目的の明確化」と「職員ファーストの設計」です。DXのためのDXではなく、スタッフの本質的な課題をどう解決し、患者と向き合う時間をどう増やすかを軸に据えること。その上で運用負荷を増やさない設計が不可欠だと思います。

渡邉様
価格や汎用性の壁はありますが、今後は家電のようにロボットもツール化が進むと見ています。適材適所で多様なロボットが動く時代に備え、インフラの標準化と柔軟なプラットフォームの整備が鍵になりますよね。
でもそれは決して病院単体・スタッフ単体でできることではない。「地域の人々も巻き込みながら一緒につくり上げて行く」ことが重要だと考えています。
知多半島総合医療センターの新たなシンボルマークには、半田市と常滑市の形と人が手を差し伸べている姿が線で表現されていますが、まさに、市民との繋がりやコミュニケーションを大事にしているこの病院だからこそ、共創の姿勢で取り組みたいですね。
ロゴマークといえば、経営統合した背景を持ちながら、病院名に自治体名が利用されていないことが意外でした。
渡邉様
知多半島総合医療センターの病院名には、あえて「半田市」や「常滑市」といった自治体名を含めていません。これは、単なる市民病院の経営統合ではなく、地域全体の急性期医療を担う中核拠点として、より広域な視点で位置づけるべきという意図があったからです。
自治体名を冠することで、市の施設という印象が強まり、他の市町との連携や将来的な拡張性が損なわれる可能性があるとの懸念もありました。
実際、病院建設と並行して行政組織から独立した法人化を進めたことも、この「広域医療圏」を前提とした設計思想の一環でした。こうした背景のもと、病院名には地域全体を象徴する「知多半島」という言葉が選ばれました。ここは非常にこだわった部分ですね。
今後この病院で目指すDXの姿、またその中で「知多半島総合医療センター × LCI」が担うポジションについてお聞かせください。
渡邉様
知多半島の急性期医療を支える中核として、DXを通じて「人間にしかできない医療行為」に注力できる環境を整備していきます。
Octa Roboticsさんとは今後も連携し 、共にアップデートを重ねながら、全国に先駆けた「医療×ロボットインフラ」のモデルを築いていきたいですね。